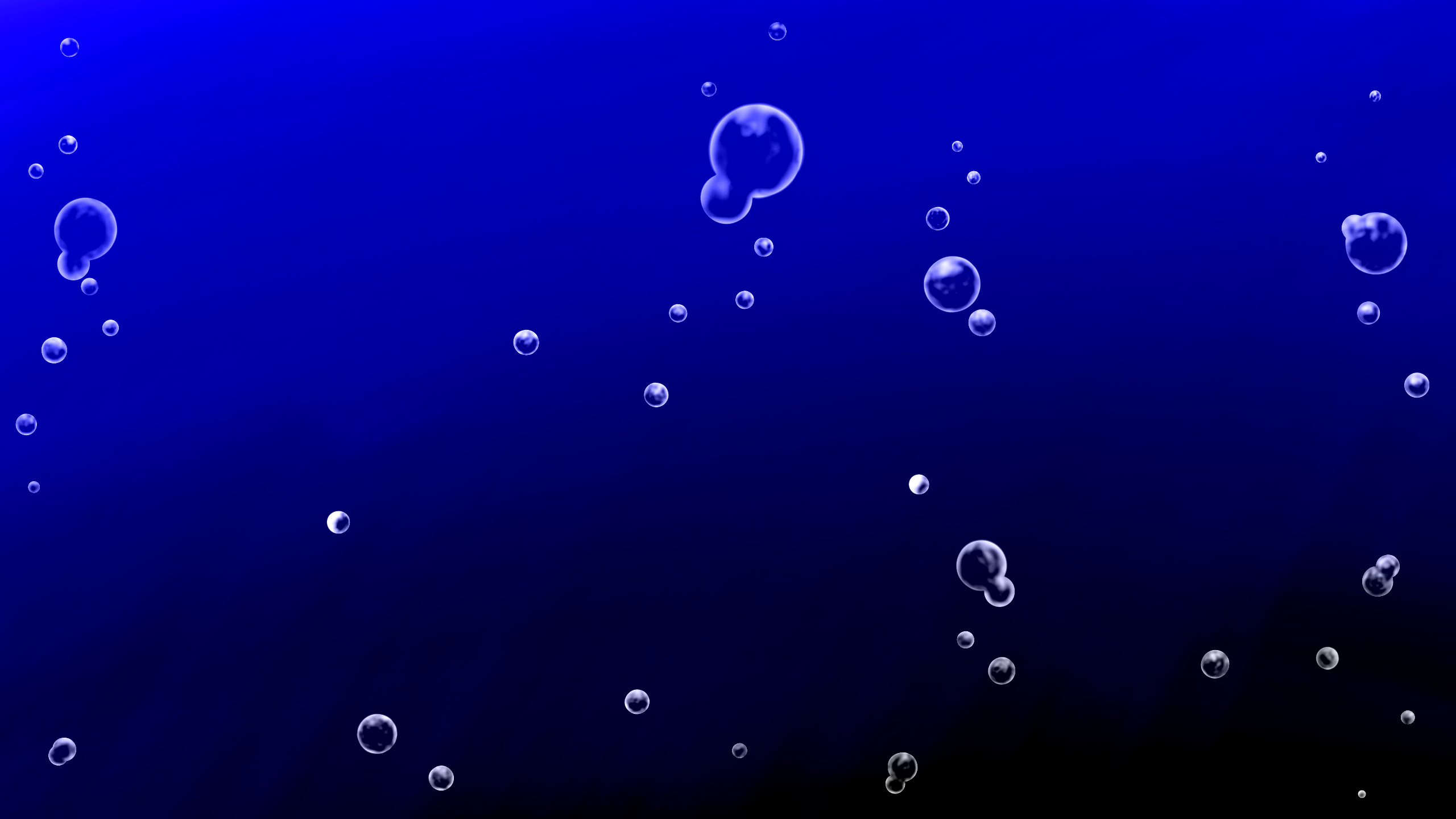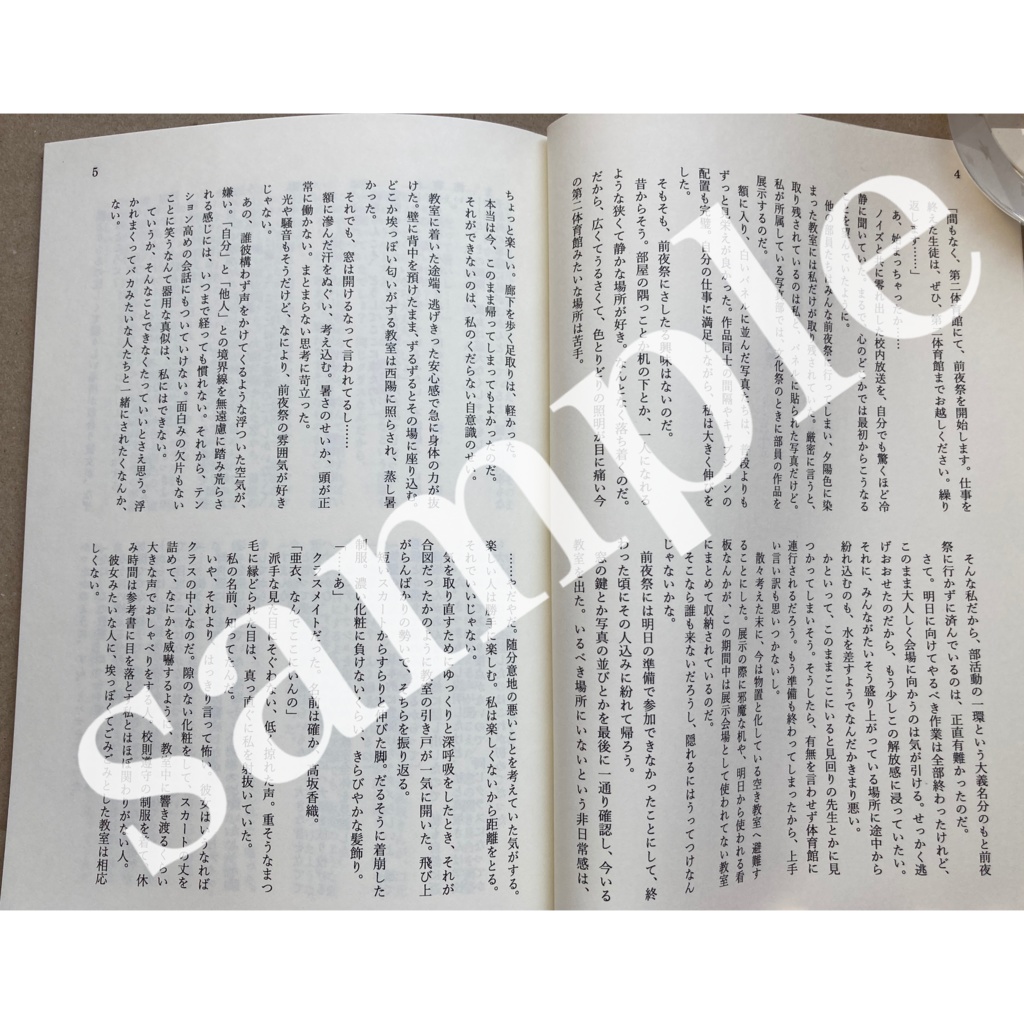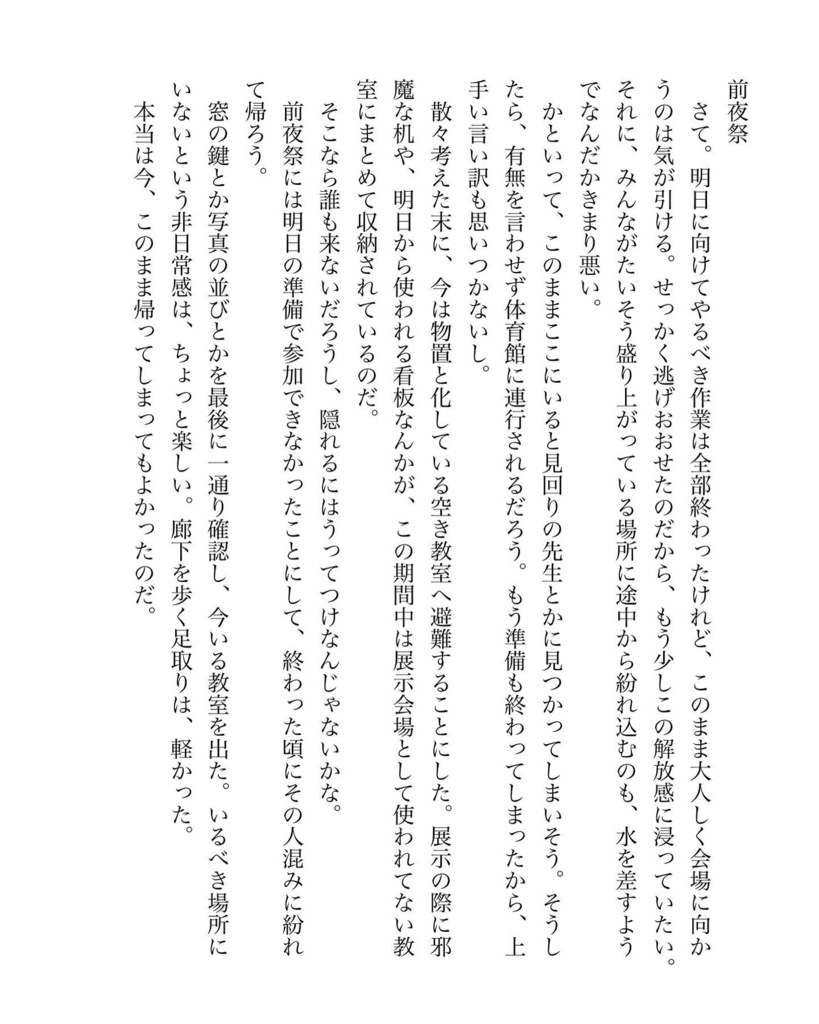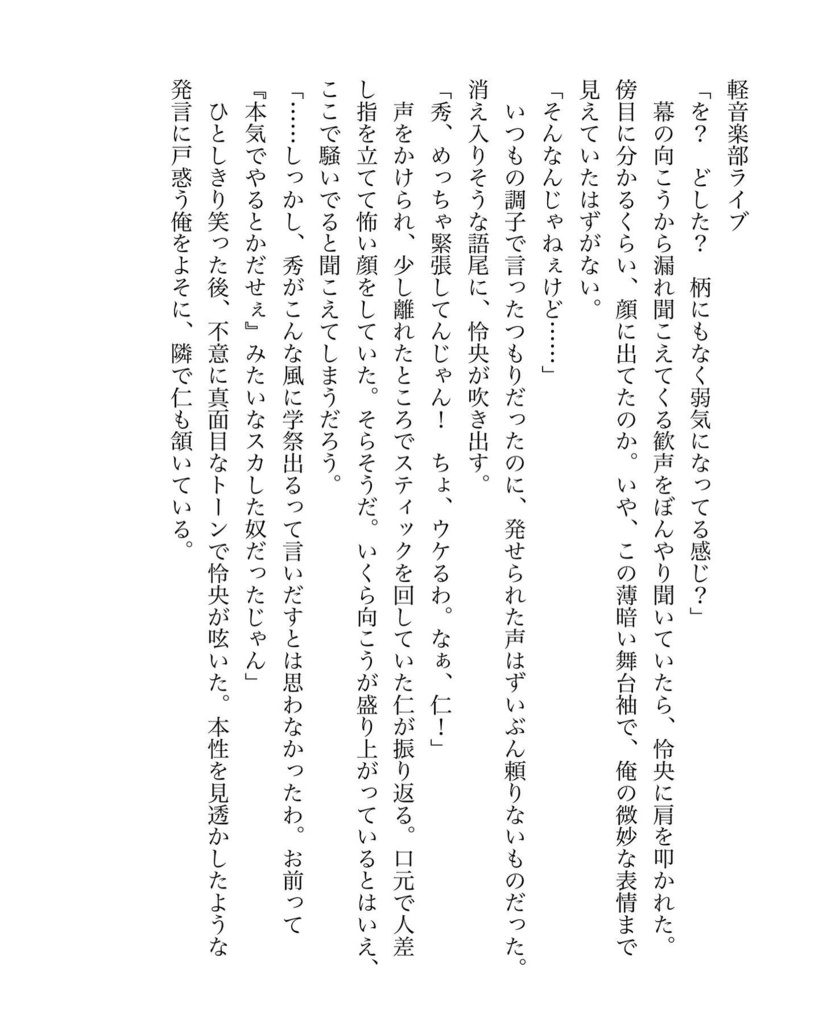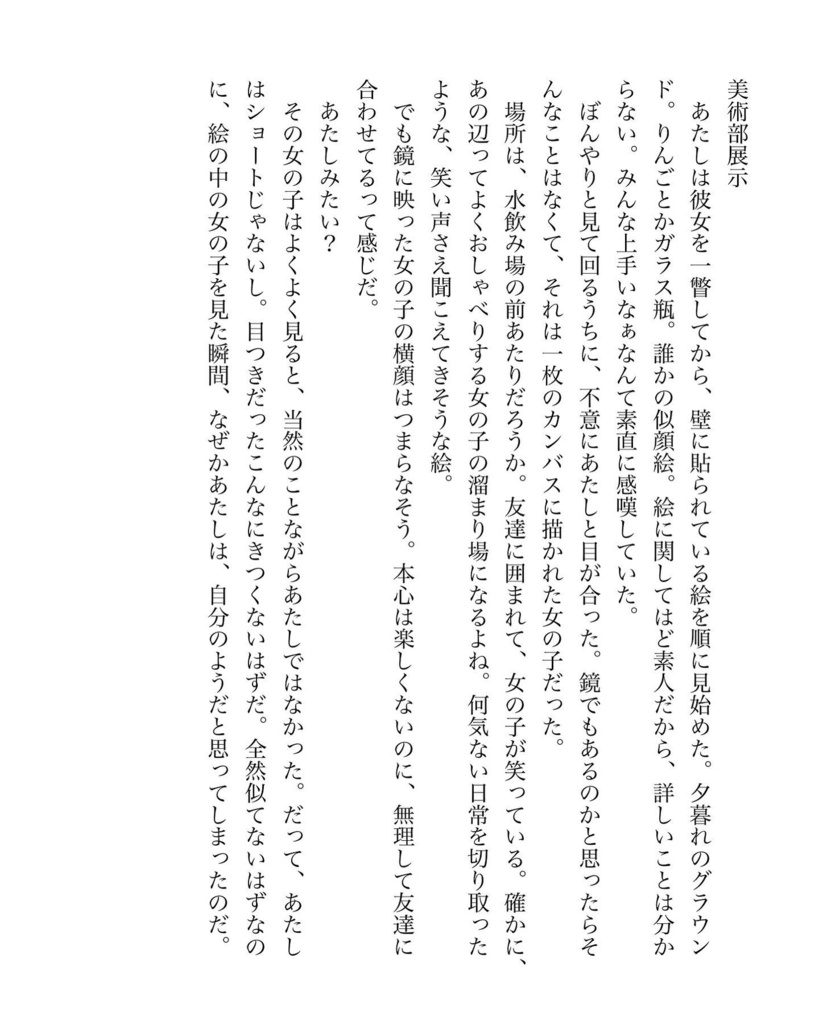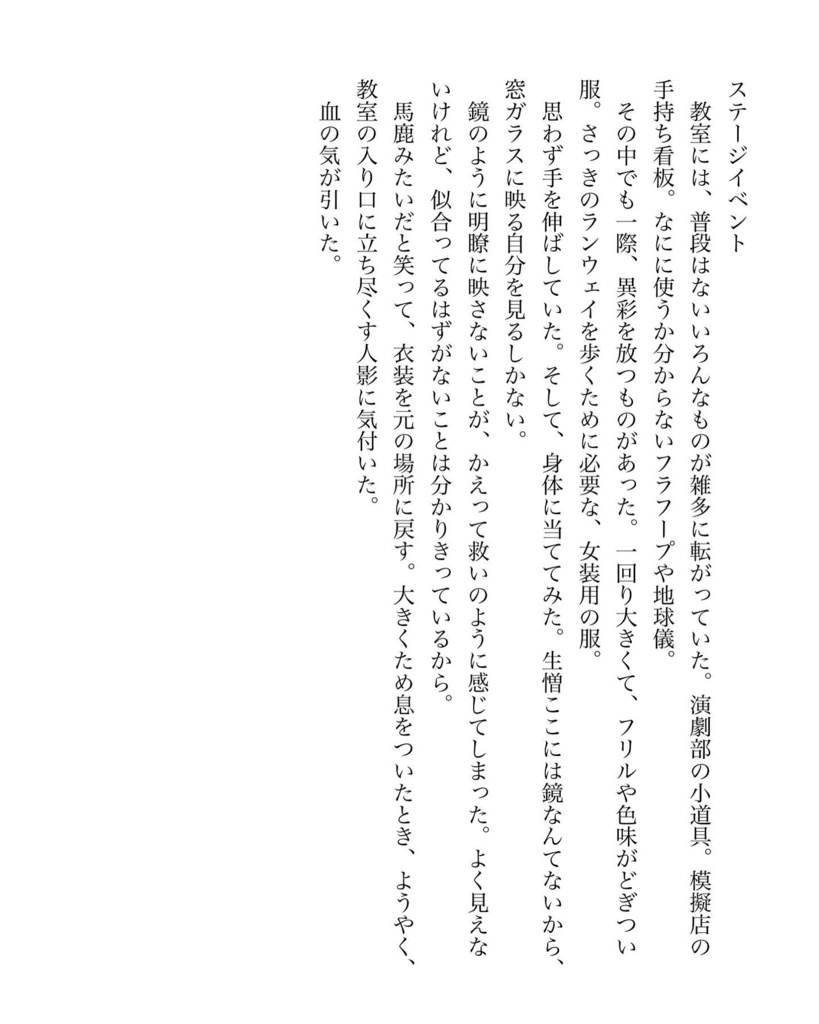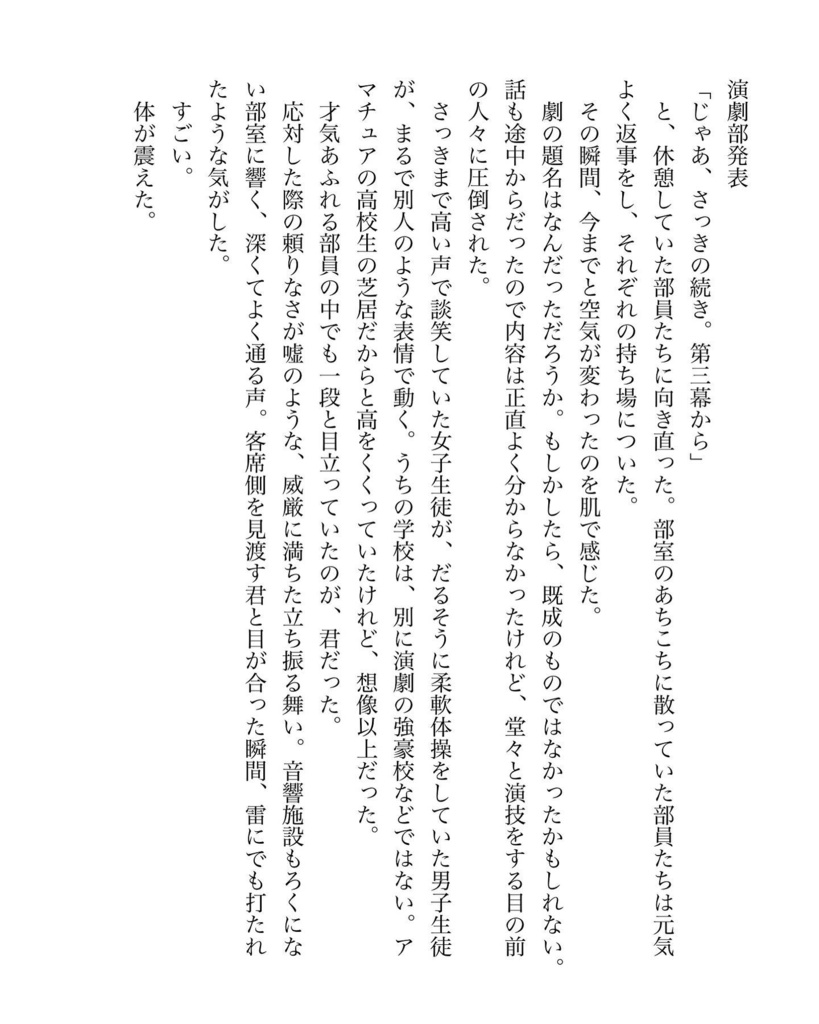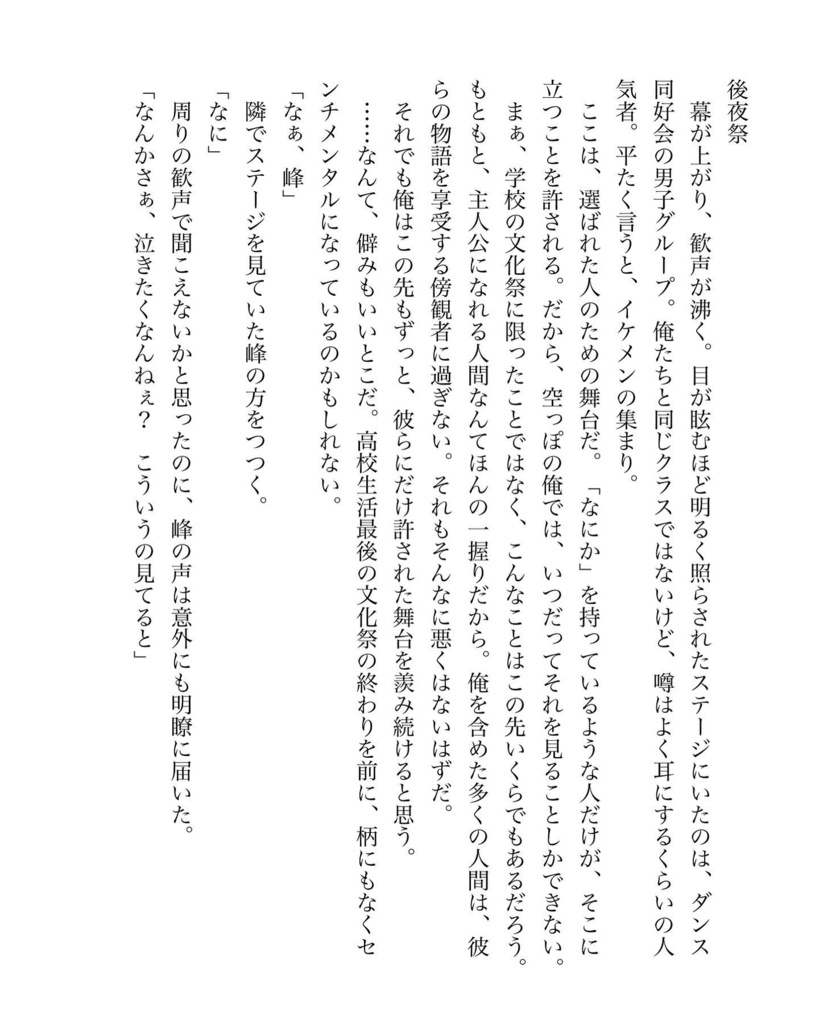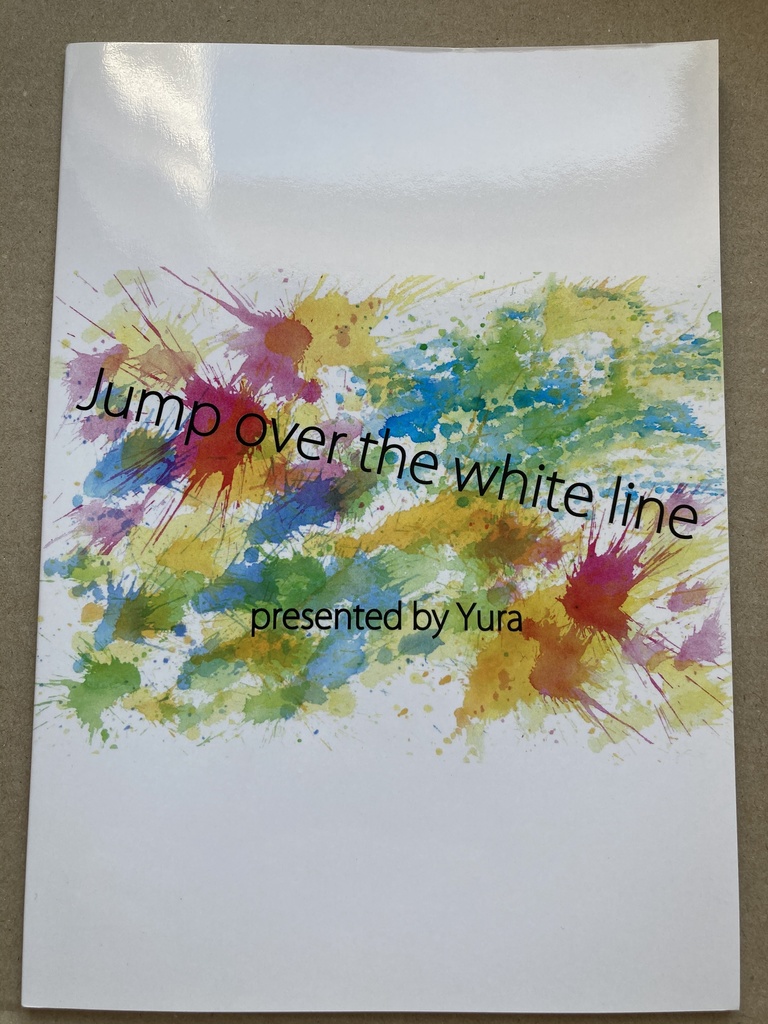白線を飛び越えて
- 物販商品(自宅から発送)あんしんBOOTHパックで配送予定支払いから発送までの日数:7日以内¥ 500
2019年3月21日の第三回文学フリマ前橋で初頒布したものです。 文化祭をテーマにした短編集となっております。 文化祭という状況の中で、いつもとはちょっと違う自分になろうとする生徒たちのお話。文化祭が好きな人はもちろん、そうでない方にもお勧めです。 ・サイズ:A5 ・頁数:52頁 ・オンデマンド本 以下、各話あらすじと試し読み。 ○「前夜祭」 →騒々しい場所が嫌いな主人公が、前夜祭から逃げるお話。 ・試し読み さて。明日に向けてやるべき作業は全部終わったけれど、このまま大人しく会場に向かうのは気が引ける。せっかく逃げおおせたのだから、もう少しこの解放感に浸っていたい。それに、みんながたいそう盛り上がっている場所に途中から紛れ込むのも、水を差すようでなんだかきまり悪い。 散々考えた末に、今は物置と化している空き教室へ避難することにした。展示の際に邪魔な机や、明日から使われる看板なんかが、この期間中は展示会場として使われてない教室にまとめて収納されているのだ。 そこなら誰も来ないだろうし、隠れるにはうってつけなんじゃないかな。 窓の鍵とか写真の並びとかを最後に一通り確認し、今いる教室を出た。いるべき場所にいないという非日常感は、ちょっと楽しい。廊下を歩く足取りは、軽かった。 ○「軽音楽部ライブ」 →とあることがきっかけで、文化祭のステージに立つお話。 ・試し読み 「を? どした? 柄にもなく弱気になってる感じ?」 幕の向こうから漏れ聞こえてくる歓声をぼんやり聞いていたら、怜央に肩を叩かれた。傍目に分かるくらい、顔に出てたのか。いや、この薄暗い舞台袖で、俺の微妙な表情まで見えていたはずがない。 「そんなんじゃねぇけど……」 いつもの調子で言ったつもりだったのに、発せられた声はずいぶん頼りないものだった。消え入りそうな語尾に、怜央が吹き出す。 「秀、めっちゃ緊張してんじゃん! ちょ、ウケるわ。なぁ、仁!」 声をかけられ、少し離れたところでスティックを回していた仁が振り返る。口元で人差し指を立てて怖い顔をしていた。そらそうだ。いくら向こうが盛り上がっているとはいえ、ここで騒いでると聞こえてしまうだろう。 「……しっかし、秀がこんな風に学祭出るって言いだすとは思わなかったわ。お前って『本気でやるとかだせぇ』みたいなスカした奴だったじゃん」 ひとしきり笑った後、不意に真面目なトーンで怜央が呟いた。本性を見透かしたような発言に戸惑う俺をよそに、隣で仁も頷いている。 ○「美術部展示」 →何気なく見ていた美術部の展示作品に、自分にそっくりな絵を見つけるお話。 ・試し読み あたしは彼女を一瞥してから、壁に貼られている絵を順に見始めた。夕暮れのグラウンド。りんごとかガラス瓶。誰かの似顔絵。絵に関してはど素人だから、詳しいことは分からない。みんな上手いなぁなんて素直に感嘆していた。 ぼんやりと見て回るうちに、不意にあたしと目が合った。鏡でもあるのかと思ったらそんなことはなくて、それは一枚のカンバスに描かれた女の子だった。 場所は、水飲み場の前あたりだろうか。友達に囲まれて、女の子が笑っている。確かに、あの辺ってよくおしゃべりする女の子の溜まり場になるよね。何気ない日常を切り取ったような、笑い声さえ聞こえてきそうな絵。 でも鏡に映った女の子の横顔はつまらなそう。本心は楽しくないのに、無理して友達に合わせてるって感じだ。 あたしみたい? その女の子はよくよく見ると、当然のことながらあたしではなかった。だって、あたしはショートじゃないし。目つきだったこんなにきつくないはずだ。全然似てないはずなのに、絵の中の女の子を見た瞬間、なぜかあたしは、自分のようだと思ってしまったのだ。 ○「ステージイベント」 →ミスコンをきっかけに繰り広げられる自己表現のお話。 ・試し読み 教室には、普段はないいろんなものが雑多に転がっていた。演劇部の小道具。模擬店の手持ち看板。なにに使うか分からないフラフープや地球儀。 その中でも一際、異彩を放つものがあった。一回り大きくて、フリルや色味がどぎつい服。さっきのランウェイを歩くために必要な、女装用の服。 思わず手を伸ばしていた。そして、身体に当ててみた。生憎ここには鏡なんてないから、窓ガラスに映る自分を見るしかない。 鏡のように明瞭に映さないことが、かえって救いのように感じてしまった。よく見えないけれど、似合ってるはずがないことは分かりきっているから。 馬鹿みたいだと笑って、衣装を元の場所に戻す。大きくため息をついたとき、ようやく、教室の入り口に立ち尽くす人影に気付いた。 血の気が引いた。 ○「演劇部発表」 →舞台に立つ君の気持ちに気付いてしまうお話。 ・試し読み その瞬間、今までと空気が変わったのを肌で感じた。 劇の題名はなんだっただろうか。もしかしたら、既成のものではなかったかもしれない。話も途中からだったので内容は正直よく分からなかったけれど、堂々と演技をする目の前の人々に圧倒された。 さっきまで高い声で談笑していた女子生徒が、だるそうに柔軟体操をしていた男子生徒が、まるで別人のような表情で動く。うちの学校は、別に演劇の強豪校などではない。アマチュアの高校生の芝居だからと高をくくっていたけれど、想像以上だった。 才気あふれる部員の中でも一段と目立っていたのが、君だった。 応対した際の頼りなさが嘘のような、威厳に満ちた立ち振る舞い。音響施設もろくにない部室に響く、深くてよく通る声。客席側を見渡す君と目が合った瞬間、雷にでも打たれたような気がした。 すごい。 体が震えた。 ○「後夜祭」 →ステージに立つ人を羨みながらも、自分を見つめ直すお話。 ・試し読み 幕が上がり、歓声が沸く。目が眩むほど明るく照らされたステージにいたのは、ダンス同好会の男子グループ。俺たちと同じクラスではないけど、噂はよく耳にするくらいの人気者。平たく言うと、イケメンの集まり。 ここは、選ばれた人のための舞台だ。「なにか」を持っているような人だけが、そこに立つことを許される。だから、空っぽの俺では、いつだってそれを見ることしかできない。 まぁ、学校の文化祭に限ったことではなく、こんなことはこの先いくらでもあるだろう。もともと、主人公になれる人間なんてほんの一握りだから。俺を含めた多くの人間は、彼らの物語を享受する傍観者に過ぎない。それもそんなに悪くはないはずだ。 それでも俺はこの先もずっと、彼らにだけ許された舞台を羨み続けると思う。 ……なんて、僻みもいいとこだ。高校生活最後の文化祭の終わりを前に、柄にもなくセンチメンタルになっているのかもしれない。